日本には「お金稼ぎ=悪」という風潮があるともいわれ、私もたしかにそれは感じるので、なぜなのかを考えてみます。
日本には「お金を稼ぐことは悪いことだ」という、風潮や意識があるといわれることがあります。
これに関しては、もしかすると、そのように思わされてきただけのことなのかもしれませんが、私もそのように考えている部分が少なからずあり、人生においてお金を稼ぐことは、そこまで重要なことではないと思っています。
しかし、それでほんとうにいいのか、と考えることもあるわけです。
現実問題として、お金を稼がなければ生きてはいけないですし、お金があるからこそできることもあります。「善」の行いをするにしても、お金がなければできない、お金を稼がなければできないこともあるでしょう。
お金、お金と連呼しているこの時点で、すでに拒否反応が出ている方もいらっしゃるかもしれませんし、私も私で思うところはありますが、いい機会なので今回は、この「お金稼ぎ=悪」という問題について考えてみたいと思います。
お金稼ぎは「悪」という風潮
おそらく、さかのぼればさかのぼるだけ、それらしい理由が出てくると思うので、今回は比較的浅めにしておきたいと思いますが、日本の歴史を振り返ってみると、いくつか「お金稼ぎは悪」とする風潮の原因が見えてくるように思います。
たとえば、日中戦争が開戦した翌年の1938年。
戦争の長期化に伴って「戦費と軍需生産力拡充のための資金は、国民の貯蓄によって賄われるべきだ」とする見解から、大蔵省の外局として「国民貯蓄奨励局」が新設されると、同年6月には大蔵大臣の諮問機関として「国民貯蓄奨励委員会」が設置。のちに地方では支局が置かれ、貯金の奨励が組織的に進められるようになりました。
1941年には、この流れを受けて「国民貯蓄組合法」が制定。この法令によって国民は、地域や職場、学校などで結成された国民貯蓄組合にかならず加入し、組合で貯金をしなければならなくなります。
それは子どもたちも例外ではなく、「一億一心百億貯蓄」などをスローガンに、国をあげて貯金が奨励されたのです。
しかし、そういった国民の努力は報われることはなく、日本は敗戦してしまうわけですが、それからなにが起きたのかというと、GHQによる占領政策の1つとして、「財閥の解体」が行われました。
この財閥解体とは、日本の経済を民主化する目的で、財閥、ようはお金持ちの一族が経営する、巨大な力を持ったグループを解散させたものですが、その真の目的については、以下のように語られることもあります。
財閥解体の目的は日本の社会組織を米国経済が望むが如く改革することでもなく、いわんや日本国民自身のためにするものでもない。その目的とするところは日本の軍事力を心理的にも制度的にも破壊するにある。『財閥解体政策の基盤とその変遷』
民主化という大義名分のもと、二度とその、恐ろしいまでに鋭い牙で歯向かってこないように、米国は日本人の牙を抜くことにした、という話です。
このような戦時中から戦後までの出来事だけでも、国民がお金を使うこと、お金を持つことはよくないことだと考えるのは、至極当然のことでもあるように考えることができます。
また、「使う、持つ」ということは、その前に「得る」ということでもあるので、お金を稼ぐことは悪いことだとする意識は、少なくとも戦時中からはあったのではないでしょうか。
(参考:国民貯蓄奨励局|アジ歴グロッサリー/貯金の奨励|ふるさとファイル「pdf」)
香港人と日本人の違い
最近読んだ本に『カジノエージェントが見た天国と地獄』というものがあります。
この本は、マカオのカジノでVIPのお客さんをアテンドする「エージェント」という仕事をしている著者が、おもにマカオのカジノで見てきたものを記したものですが、著者がエージェントになる前に香港を訪れた際に感じたこととして、このようなことが書かれていました。
日本では「お金」の話はよくないこと、悪いもの、人前でしてはいけないものという嫌金思考が根付いており、お金の話を持ち出すことは何かと敬遠されがちです。でも、香港では誰もが世間話をするかのようにお金の話をします。……香港の人たちは、小さい頃から「お金」というものの大切さを教えられます。だから、金融に対するセンスや知識が、日本人の何倍も備わっているのです。『カジノエージェントが見た天国と地獄』p.161
とくに前半に関しては、私は読んでいてうなずくしかなく、後半に関しても、たしかに小さいころにお年玉などの大きなお金をもらったときは、両親から「貯金をしなさい」とはよくいわれたものですが、なぜ貯金をするのか、貯金をするとどうなるのか、もらう以外の方法で貯金をするためにはどうすればいいのか、といったような深いところまでは、家でも学校でも教わることはなかったように思います。
「日本はお金(金融)の教育をしない(遅れている)」ともよくいわれますが、いま思えば、実際にそうだったようにも感じます。
人前でお金の話をしないで一定期間が過ぎれば、人前でお金の話はしないほうがいいのではないか、と思うようになってもおかしくはないでしょう。子どものころに食べなかったものは、大人になっても食べないのと同じようなことです。
世界中の教育現場をこの目で見てきたわけではないので、はっきりしたことはいえませんが、日本のお金に対する教育が弱いとされていることも、この「お金稼ぎ=悪」という問題が生まれることに関係があるのかもしれません。
ただ、私はそれ以上に、これもまた問題視されることが多い「教育方針」にこそ、問題があるのではないかと思っています。
日本の「みんな同じ」教育方針
これに関しては日本だけがそうなのかはわかりませんし、時代が変わって改善されているということもあるのかもしれませんが、日本の「みんな同じ、出る杭は打たれる」とでもいったような教育方針は、空気を読むという日本人のすばらしい能力を発現させる代わりに、抜け駆けは許さないという同調圧力をも生むように思います。
少なくともまだ私が子どものころは、独学で学んだものを授業で使おうものなら、教師からは「それはまだやっていないし、みんながわからないから使うな」と注意されたものです。
どうして周りに合わせないといけないのか? 先に進みたいと思う者への道を、なぜ指導者である先生が閉ざすのか?
子どものころの私にとっては疑問でしかなかったのですが、教育の現場では教師が正義であるので、すべての生徒はこれに従わなければなりません。逆らおうものなら、教師や周りの生徒からは「敵」として認定されてしまうこともあるでしょう。日本人は子どものころから空気を読まなければならないのです。
さて、このような教育方針が変わっていなければ、子どもの没個性化が進んでしまうようにも思いますが、それが問題となるのは、その子どもが社会人になって、自分でお金を稼ぐようになってからが本番であると私は思います。
1人だけお金を稼ぐのは許さない?
厚生労働省によって2019年に行われた「国民生活基礎調査」では、日本の所得状況の割合は200万~300万円が13.6%で最多となり、300万~400万円が次点で12.8%、100万~200万円は僅差の12.6%で3番目に多く、平均所得金額(552万3000円)を下回る割合は61.1%という結果が出ました。
また、生活への意識調査では、「苦しい」または「大変苦しい」と回答した割合は54.4%にものぼり、「ゆとりがある」または「大変ゆとりがある」という回答は、わずか5.7%となっています。
この調査結果から、日本では生活に余裕がない人のほうが圧倒的に多いことがわかりますが、このような状況下において、いくらもうかっている、いくら稼いだといった、タブー視されることもあるお金の話をすれば、大多数の人のあいだで、ある感情が引き起こされるのは必然となります。
これまでみんな同じでやってきたのに、どうして一部の人間だけがゆとりのある生活をしているんだ、という「ねたみ」。お金がある人間がいる一方で、自分だけお金がないのはおかしいじゃないか、という「ひがみ」。
ようするに「嫉妬」の感情がわき起こるのです。
嫉妬の感情を持つことは人として当然のことだと思いますし、これは全世界共通の感情だとは思いますが、とくに日本の場合は、教育のせいかどうかは定かではないものの、いつのまにか生まれた同調圧力があるので、お金を稼いでいる人に対してはより増幅された嫉妬の感情が向けられるように思います。
みんな同じでやってきた。出る杭は打たれなければならない。空気を読め。抜け駆けは許さないぞ。ルール違反者は糾弾されるべきだ!
その感情は、いつしか懐疑的で批判的、かつ攻撃的なものとなり、大多数がそれを共有することになれば、「お金を稼ぐ」ことは仲間に対する裏切り、つまり「悪」になります。
このような一連の流れがあることで、「お金を稼ぐ=悪いこと」という風潮ができていくのではないでしょうか。
恐怖から人を守る美学という名の鎧
私はこれまで、飲食関係の仕事を長年続けてきました。その目的は、自分のためというよりかは、お店のため、お客さんのためであり、お金を稼ぐことはほとんど考えてきませんでした。
年収は200万円以下になることや、やっていけるかどうかもわからない生活を受け入れてでも飲食の仕事をやめた(休業している)のは、当ブログの運営作業に専念するためであって、これも基本的には人のためと思っての決断でした。
そこでも、お金を稼ぐことは重要な要素ではありませんでした。それが私にとっての美学のようなものだと考えていたからです。
お金がなくてもやりたいことをやっていればいい。たとえお金がないまま死ぬことになろうとも、それこそが武士道精神であって、大和魂であり、美しいのだと。
しかし、今回の問題を考えるにあたって、じつは私は、美学という名目の鎧をまとっているだけで、ただおびえているだけなのではないかとも考えるようになりました。
現実問題として、私には返さなければならない奨学金であったり、老朽化が進む実家の改装や、自分の城(店)をつくるといった夢や目標、課題がありますが、それらをするにはけっして少なくはないお金が必要となります。
ところが私は、なにかそういった「やりたいこと」があるというのに、どこか現実として受けとめることができておらず、いまの「とりあえずは生活できる」という状況に満足してしまっているような気がするのです。
やりたいことを成し遂げるには、お金を稼がなければなりません。お金を稼げば、少なくはないであろう批判の目や嫉妬にさらされることになるかもしれませんが、それを乗り越えていかなければ、なにかを叶えることはできません。でもそれは、とてもむずかしいことであり、現状維持のほうがはるかにらくです。
私はいま、ほんとうは美学ではなく、「お金稼ぎ=悪」という風潮と、低所得という現実の鎧に守られている?
お金は二の次だ、美学だ、などといっているのは、大多数からの加護を受けることができる鎧を脱ぎ捨てるのが、ただ恐いだけなのではないか。手を伸ばせばつかむことができる武器を、その手に取る勇気がないだけなのではないか。
夢物語ばかり語っていないで、もう少し現実にも目を向けたほうがいいのではないだろうか、と今回は考えさせられました。
今回のまとめ
・歴史や教育、国民性が関わっているのかもしれない
・批判にさらされてでも武器を取らなければならないときはたぶんある
私が当ブログの集客をほぼSEO(検索)のみに絞っているのは、私がいうところの美学によるものですが、裏を返せば、集客が増えることによって批判的な目線を向けられる可能性が上がることを、ただ恐れているだけのことなのかもしれません。
ブログでもなんでも、収益を上げて、次へ、また次へと進んでいくためには、集客は必須となると思います。そのための武器(集客ツール)を使うか使わないかは人の自由ではあるものの、美学と恐怖を混同してはいけないと今回の件で感じました。
なお、これは保身のためにいうわけではありませんが、お金を稼ぐことは悪いことではないと私は思います。
悪いのは汚い手段を使うことや、成金のような連中の立ち振る舞いであって、真っ当な手段でお金を稼いでそれを使えば、経済も回りますし、それによって助かる人もいると思うからです。
もちろん、誰かが稼ぐことで誰かが損をするということもあるとは思いますが、これは損をした人が別の方法を編み出すなどして競争していけば、より洗練されたものが残っていき、結果的に社会は豊かになっていくと思うので、それはそれで仕方がないことのような気もします。
いずれにせよ、批判を恐れない精神力です。お金を稼ぐにあたっていちばん重要なことは、もしかするとこれなのかもしれません。

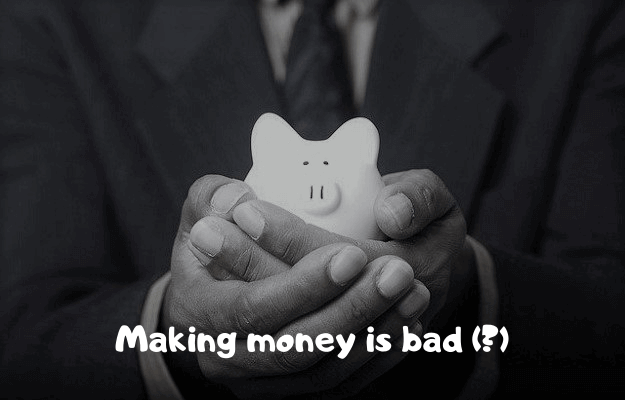
コメント(確認後に反映/少々お時間をいただきます)