英国の哲学者の言葉に「知識は力なり」というものがあります。精神疾患を克服するためにも「知る」ことは必要ですよ。
精神的な病を克服するためには、まずはなにから始めるべきなのでしょうか。
私は、自身の心と身体に起きている変化を正しく知ることこそがスタートラインだと思っています。それをすることで、正しい選択ができるようになっていくのもそうですが、知識はあとになっても大きな力となってくれるに違いないと思うからです。
まずは心の病気について知り、理解を深めていくことが大事だと私は思っているので、今回は知ることの重要性についてお話しします。
大切なのは敵と自分を知ること
少し趣向を変えて、時は戦国時代。そこに敵城を落としたいと考えている武将がいたとして、彼は出陣するまでのあいだになにをするでしょうか。
きっと自軍の情勢を把握し、装備を整え、馬や食料の準備をするでしょう。そして敵軍の様子や地形などを偵察して戦略を立てると思います。
そこで本題ですが、中国の兵法書『孫氏』の有名な一節に以下のものがあります。
これは、敵と味方の情勢をよく知ったうえで戦えば、何度戦おうとも敗れることはないということを意味しています。
孫子の言葉を借りるならば、「精神疾患」という敵と「自分自身」という味方を熟知したうえで戦いに臨めば負けることはない、と言うこともできるかもしれません。敵を倒すためには、病気と自分自身について知ること、理解することが大切なのです。
また「知る」ことで、現在薬を服用している場合、薬の量が多すぎるのではないか、自分の症状と合っていないのではないか、といった判断をすることもできます。
なかには適切でない量・内容の薬を処方する精神科医もいます。薬が合っていなければ根本的な治療の妨げにもなるので、人任せにはせず、自身でも判断できるようになるといいと思いますよ。
若かざれば則ち能く之を避く
一方で『孫氏』にはこうも書かれています。
意訳すると、戦況が不利であれば退却し、まったくかなわないのであれば戦わない。
これは戦うのをやめて諦めろと言っているわけではありません。病気について、そして自分自身についてをよく知ることで、避けるべきときは避け、時を見定めたうえで、戦うべきときに戦うといった判断ができるようになるということです。
精神的な病は周りからも理解が得られにくいため、自身が病気のことをきちんと理解していなければ、良くなるものもそうはなりません。「これは甘えだ、できないと思うからできない、できるまでやり続けろ」といった、精神論でなんとかなるようなものではないのです。
退却し、一度態勢を整えることは戦うことをやめるわけではありません。最終的に病気という敵に打ち勝つための準備なのです。
精神疾患とはそもそもの話、なんなのか
そもそも精神疾患とはなんのことをいうのでしょうか。精神福祉保健法では精神障害をこのように定義しています。
精神保健福祉法の対象とする精神障害者は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質そのほかの精神疾患を有するものです
これは福祉制度上の定義であり、この条文では漠然としていてわかりにくいのですが、一般的には精神疾患とは脳に異常や問題が起こることで生じる疾患(病気)や、それによって心や体、行動に変化が起こる状態のことをいいます。
精神疾患にもさまざまな症状があり、現在もその原因などすべてが解明されたわけではありません。しかし、そのなかの1つである「うつ病」は、脳の神経伝達物質というものに異常が起きているというのがもっとも有力とされています。
これはうつ病に限らず、その他の精神疾患にも大きく影響するものなので、以降、うつ病の原因について見ていきながら、病気への理解を深めていきたいと思います。
こころの病気とは
最近では「こころの病気」という呼び方をよく聞くようになりました。
これは精神障害といった表記と比べると印象がやさしくなる、やさしく聞こえるというのもあると思いますが、病気によってひどくこころが傷つき、いたんでしまうからといった意味もあるのかもしれません。
傷ついたこころは、自分らしさを失わせてしまいます。こころの病気を正しく理解し、本来の自分らしさを取り戻しに行きましょう。
次回からは具体的な病気の原因や、そこから考えられる根本的な原因を正す方法について見ていきたいと思います。

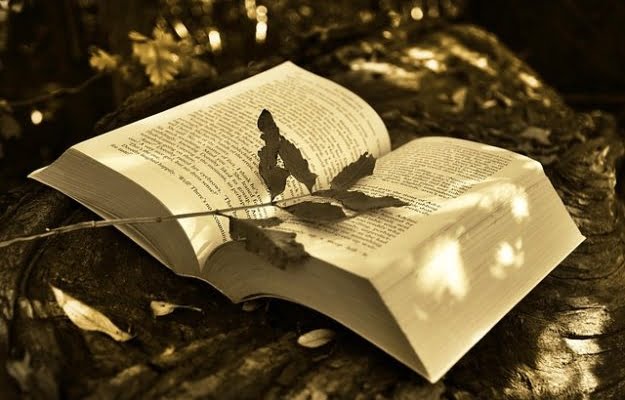
コメント(確認後に反映/少々お時間をいただきます)