バーに存在する暗黙の了解や紳士協定といったルール。その効力は、すでに失われてしまっているのかもしれません。
暗黙の了解(マナー)とは、なにかをしたり、なにかを利用したりするのであれば、知っておいて当然というルールのことをいうもので、バーにもこの「暗黙の了解」はあるのですが、バーにおけるそれは、しだいに崩壊しつつあると私は感じています。
この問題に関しては、日本の景気であったり、企業の体質であったり、そういったものもすくなからず関係はしているでしょう。しかしながら、結局のところこれは、教えてくれる人がすくなくなってきているから「よくわからない」という話なのではないか、と私は思うわけです。
事前に知っているからこその暗黙のマナーであって、事前に知る機会がないのであれば、暗黙もなにもありません。
そこで、趣向を変えて今回は、バーのルールやマナーにはこういうものがあるといった話ではなく、この暗黙の了解の存在がうすれつつあるとする原因と、なぜ私がバーのマナーについて当ブログで解説しているのか、という話をすることにしましょう。
暗黙の了解(マナー)は崩壊しつつある
冒頭でもすこしふれましたが、そもそも暗黙の了解とはなんなのかというと、口に出して明言したり、言葉として表記せずとも、当事者間での理解・納得が成立しているルールのようなもののことをいいます。
これをバーの場合で簡単にいうと、バーを利用するお客さんが(お店やほかのお客さんに対して迷惑にならないようにするための)事前に知っておくべきルールやマナー、または常識のこと、ということができるでしょう。
かつてはこのようなルールやマナーは、上司から部下へ、先輩から後輩へ、あるいはお客さんからお客さんへと、さまざまな方法で受け継がれ、バーテンダーがいわずとも、知っているお客さんのほうが多かったと私は聞かされてきました。
しかし私が思うに、この流れは途絶えかけているような気がするわけで、そう思う理由としては、おもに以下の4つをあげることができます。
- バー業界の衰退
- 若い世代をバーに連れてくる機会の減少
- お客さん同士での注意は危険なケースも
- 時代の変化とともに出現し始めた新たな「神」
まずはこれらの理由について、それぞれ補足していくことにしましょう。
1. バー業界の衰退
私には7年ほどの現場経験があり、これはそこで見てきた現場の状況や、つきあいのあるバーであったり、そこから派生したさまざまなバーで聞いた話など、それらを総合しての判断となるのですが、日本のバー業界は確実に衰退してきています。
バー業界が衰退するということは、それだけバーをおとずれるお客さんが減るということで、必然的に「暗黙」を知るお客さんの数も減っていくということ。そして、これも関係して、2つ目の理由が引き起こされるのです。
バー業界が衰退してきているとする理由
→バーテンダーは今後どうなる?全盛期からは衰退したバー業界の将来を予測
2. 若い世代をバーに連れてくる機会の減少
相対的に見てバーをおとずれるお客さんが減っているのであれば、上司と部下、先輩と後輩といった、「若い世代を連れてくるグループ」も減少しているものと考えられますが、じっさいに現場で見ていても、これは以前とくらべて減ってきていると感じていました。
これに関しては、このご時世、上司や先輩と一緒に飲みたいと思う人がすくなくなってきているから(仕事関係はとくに)というのもあるのではないでしょうか?
仕事がおわったら早く家に帰りたい。有意義な話ならともかく、説教を延々と聞かされることになるのであれば、その時間の金をくれ。
あらゆる面できびしい状況を強いられる現代社会では、とりわけ若い世代の方は、そう思うのも当然というものですよね。
さらにいうと、部下や後輩が粗相をしていてもとがめないだけならまだしも、上司や先輩のほうがマナーがわるい(つまり上司・先輩もマナーを教わっていない)といったこともじつはよくある話。
ようは、こういった事例から見ても、ひと昔前どころかそれ以上前から、上司や先輩が、部下や後輩にバーのマナーを教えてあげるという流れは、消し飛んでいるのではないか、と私は思うのです。
3. お客さん同士での注意は危険なケースも
かつてのバーであれば、バーのルール的にアウトなお客さんがいれば、ほかのお客さんが注意をすることも多々あったといいます。子どもをしかる「カミナリオヤジ」みたいな人が、街にひとりはいたのとおなじような話です。

君さ、マスターに迷惑かけちゃいかんよ
そういった、お店を助けてくれるお客さんも、かつては数多く存在したと。
しかし、いってしまえば他人になにをされるかわかったものじゃないこのご時世では、そういうわけにもいきません。
お酒を飲んで周囲に迷惑をかける人は、マナーやルールがおよばない範囲で一定数存在しますし、なんだか年々増加しているような気がしますが、こういった人は、頭がぶっ飛んだ狂戦士のような状態となることもあるため、注意したほうが、なにかしらの危害を加えられるといったことも起こりうるからです。
「記憶にございません」
あとから出てくる言葉はお決まりのせりふ。その間に、喧嘩・流血沙汰・警察騒ぎなどがあったとしても、「狂戦士」はなにもおぼえていないのです!(そこまでのことが起こるバーはさすがに少数派ですが、やはりあることはあります)
お客さんがほかのお客さんに注意するのは、現代は、残念ながらリスキーな時代だといえるのではないでしょうか?
4. 時代の変化とともに出現し始めた新たな「神」
モンスタークレーマーとか、モンスターカスタマーだとか、だいたいこの手の異名がつけられるのは「神」を自称する人たちだと思うのですが、こういう人は基本的に、自分のことしか考えていません。
それが転じて自分さえよければいいになってしまい、暴力性などが増幅され、まわりが見えない横柄な神(自称)になってしまうのだと思います。そして、そうなってしまうとこの手の人たちは、だれがなにを言おうが聞く耳を持ちません。
なにかしらの権力を持つことでそのように変わってしまう人もいますが、ひとたびへんげしてしまえば、まわりのお客さんが止めようが、バーテンダーに注意されようが、彼らはもう止まらないのです。
ニューゴッドの誕生……。
新たな神に暗黙の了解などは通用しません。なぜなら、神自身が公然のルールだから。
余談:若者にバーでいわれたこと
なんでもかんでも時代のせいにするのもどうかと思いますが、さきのような一連の流れがたしかにあるように、すくなからずそういう時代にはなってきているような気がしますし、時代の変化とともに、バーのルールやマナーといったものは、だんだんと知っている人がすくなくなってきていると私は思うのです。
また、これは余談になりますが、以前こんなことがありました。
お店に来店されたのは片方は先輩、もう片方は後輩という関係の男性2人組。私もこれまでいろんなトラブルがあったのでなんとなくわかるのですが、先輩のほうから、なにかをやらかしそうな気配がバシバシと伝わってきます。
そして、入店後しばらくすると、案の定といったふるまいをしはじめる先輩男性客。
そのやらかしっぷりはすでにアウトラインを超えていたため、私が声をかけると、注意されたのが気に入らなかったらしく男性は逆上。結局はそのまま帰られるということになったのですが、そこで後輩男性客がこういったのです。

たしかに、今回は間違いなく先輩が悪いと思うんですけど、一応先輩の手前、いわせてください

うかがいます

やってはいけないルールがあるのであれば、さきにどこかに書いてないとわからなくないですか? それもなしに注意されるのは違う気がするんですけど
たしかにそう。彼のいうことにも一理あるわけです。
私はこういったことが起こるたびに、なにかほかの方法はなかったのか、もっといい方法があったのではないか、といつも模索するようにしていました。
とはいえ、さすがに彼のいうように、店じゅうに注意事項が書かれた紙を張り付けるわけにはいかないですし、ルールブックを作成して置いておく、というのもやはりむずかしい話でしょう。
では、どうするのがいいかと考えていくと、バーを利用するのであればルールやマナーは知っていてあたりまえという風潮自体がよくないのではないか、というところにいたるわけです。
この問題をなんとかしなければならない時は、すぐそこにまで近づいているのではないだろうか? 私はこのできごとを機に、そう切実に感じるようになっていったのです。
ルールやマナーは知っていて当然という風潮がそもそも古い
バーを利用するのであれば(ルールやマナーは)知っていて当然という風潮。
それこそがバーにおける暗黙の了解の正体だと思うのですが、さきほども見てきたように、暗黙の了解は正しく機能しない時代に突入してきているわけで、もはやだれもがルールやマナーを知っている時代ではないと私は思うのです。
じつをいうと、この知っていて当然という風潮は、根深い部分もあります。バーによってはなにも教えてくれず、「暗黙」への違反があれば、突然そっけなくされたり、店主が不機嫌になったり、急に帰ってくれといわれたりすることもざらにあるでしょう。
それはさきのとおり、お客さんも聞いてくれる人ばかりではないという背景や、「自分だけよければいい、まわりのことなんか知らん」といったお客さんには、いっても通じないという問題点もあるため、いたしかたない部分があるのもたしかなことだとは思います。
では、ほんとうにただなにも知らなかっただけという人は、いったいどうなってしまうのでしょうか?
知りたくても、まちがったことをしてしまえば、だれも教えてくれず、なぜか冷たくされておわり。
それではいつまでたってもバーのルールやマナー知ることはできないですし、そんなことがつづけば、バーという場所がいやになってしまってもおかしくはありません。バーに行ったことがない方からすれば、バーの扉をひらく気にさえもならないでしょう。
かつては、お金を払ってでも学ばせてもらいたい、いやな思いをしてでも仲間に入れてもらいたいと、そうやってこの暗黙の了解を学んできたりもしたものですが、もはやそんな時代ではありません。
知りたいと思ってくれる方、バーに興味を持ってくれる方がひとりでもいる以上、だれかがやらなければならないことなのではないか、と私は思うのです。
バーのマナーを当ブログで解説している理由
私の経験上、バーのことをもっと知りたい、マナーやルールを教えてほしいと真剣に話を聞いてくれるのは、若い方や初心者の方に多いという印象がありますが、私はそういった方が「暗黙」の風潮が強いバーに行かれたさいに、いやな思いをしてほしくはないと思っています。
このご時世、マナーやルールを教えてくれる人が身近にいるということは、ほとんどないことなのかもしれません。それを知っているはずのバーテンダーでさえも、教えてくれなかったりすることもあるわけですから。
ただ、その店側の「沈黙」という選択肢(教えてくれない)は、あまりいいものではないような気もするわけです。
バーテンダーの仕事は、なにもお酒をつくることだけではありません。バーの文化をのこしていくことも仕事のひとつだと思いますし、お客さんにマナーやルールを知ってもらうことも、バーの文化をのこしていくことにつながると私は思っています。
だれもが理解しあえるきれいな世の中なんてものは、ユメやマボロシの世界の話ですから、すべての人にマナーを理解してもらうのは、かぎりなく不可能に近いでしょう。
しかし、だからといって、理解してくれる可能性までをもバーテンダーがみずから摘んでいたら、最終的には、なにものこらなくなってしまうという話なのではないでしょうか?
私が当ブログでバーのマナーを解説している理由、それは、バーに興味を持ってくれ、知りたいと思ってくれる方が安心してバーに行けるため、そして、バーの文化を存続させるためです。
知っている人だけが来ればいい。そのスタンスはじっさいにらくなものですが、それをつづけていれば、これからの時代のバー業界はきっと、そのまま先細りになっていくだけでしょう。
また、お客さん側が知らないことは、なにも恥ずかしいことではなく、ほんとうに恥ずかしいのは、知ろうともせずに自分のわがままを押し付けることだとも思います。
だからこそ、マナーやルール、そういったわからないことがあればバーテンダーに聞いてみてほしいと思いますし、そもそもなにを聞けばいいかもよくわからないという方もいらっしゃるはずなので、当ブログでは、そういった「暗黙」を解説することにしています。
今回のまとめ
・ルールやマナーは知っていて当然という風潮は強い
・沈黙のバーテンダー(教えてくれない)もけっこう多い
バーにはさまざまなマナーやルールがありますし、お店によってもそれは異なるため、正直いうと、こういった暗黙の了解は面倒くさいと感じる方もすくなくはないと思います。しかし、その面倒くささのさきに、それ以上のおもしろさがあることを、私は皆さんに知ってもらいたいと思っています。
人はいつからでも、いくつになっても成長することができるもの。若いとか、若くないとか、年齢なんてものはそこに関係はありません。大事なのは、みずから知ろうとすることとと、ある意見に対して頭ごなしに否定せず、いったん自分のなかで考えてみることなのではないでしょうか?
ルールやマナーを知っていると、お店や、お客さんから「仲間」として認識される確率が飛躍的に上がります。
人と人とのつながりや、つきあいが希薄になっているこんな時代だからこそ、紳士淑女の社交場としての側面を持ち、困っているときは助けてもらえたり、知らない世界を教えてもらえたりすることができるバーの楽しさを、ぜひとも体感してもらいたいと私は思っています。

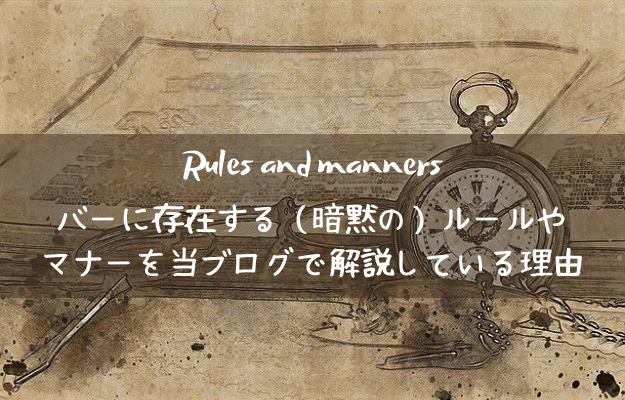
コメント(確認後に反映/少々お時間をいただきます)