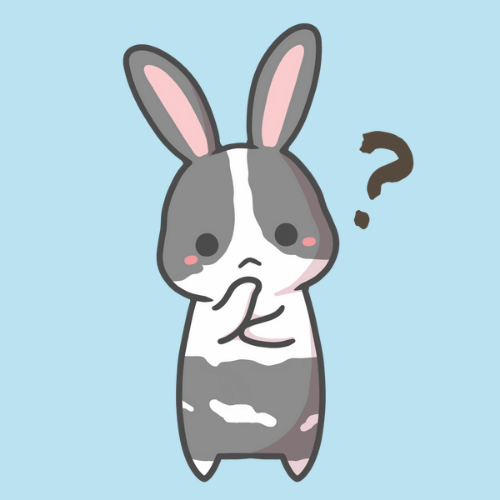 イブスター店長
イブスター店長毛球症とな?
うさぎさんのなりやすい病気に「胃腸うっ滞(毛球症)」があります。
うさぎさんがご飯を食べられなくなり、動けなくなってしまう……というものですね。
では、これは自然に治るのか? といった、うっ滞に関することを本記事ではお話ししていきます。
- 胃腸うっ滞(毛球症)とはなにか
- うさぎが胃腸うっ滞になったときの対策方法
- 胃腸うっ滞を予防するにはどうすればいいか?
胃腸うっ滞とは、なんらかの原因によって、うさぎさんのおなかでモノが詰まったりする病気です。



それで、これはもともと、毛が詰まって起こるものと考えられていたので、
かつては「毛球症」とよばれていました。
しかし近年では、その認識(毛が詰まって起こる)が見なおされてきています。
- では、どう認識が見なおされたのか?
- 胃腸うっ滞と毛球症の違いはなにか?
それをまずは確認していき、そのあとで対処方法として、自然回復の可能性も見ていきましょう。
今日からできる「胃腸うっ滞の予防方法」もあわせて紹介するので、どうぞこちらもごらんください!
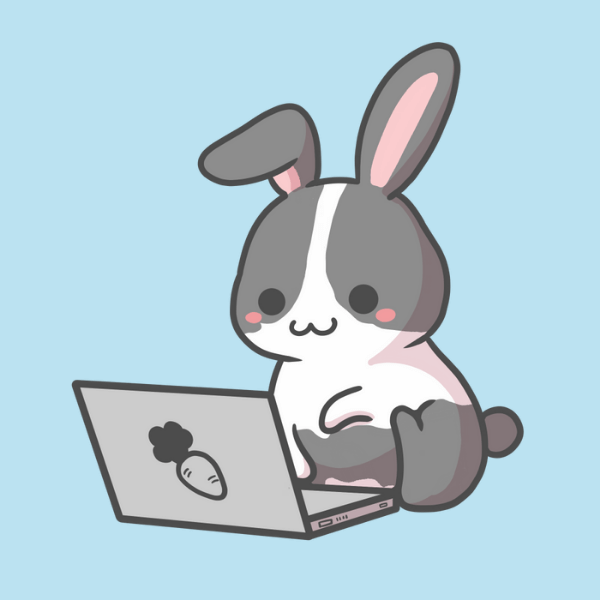
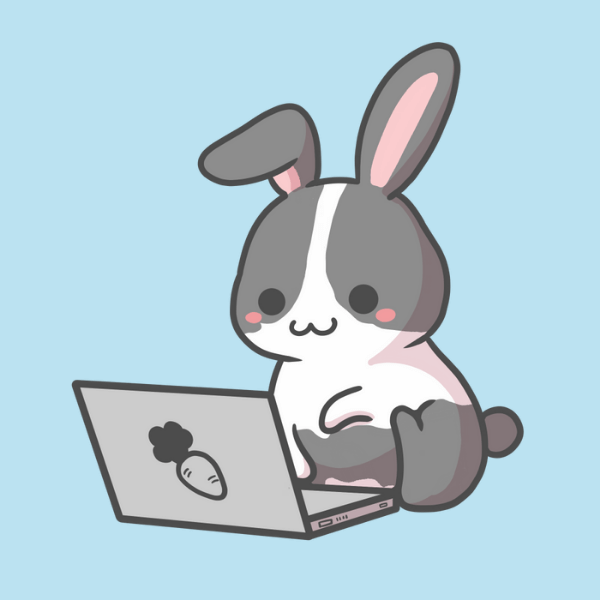
この記事に登場するうさぎ
- ミニレッキスのイブスター店長
- 2016年11月生まれのオス(現在7歳)
- やや詳しいプロフィールはこちら
うさぎの胃腸うっ滞(毛球症)
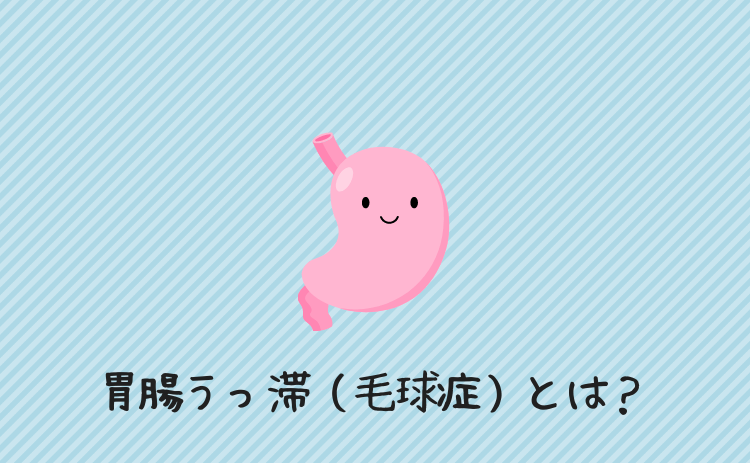
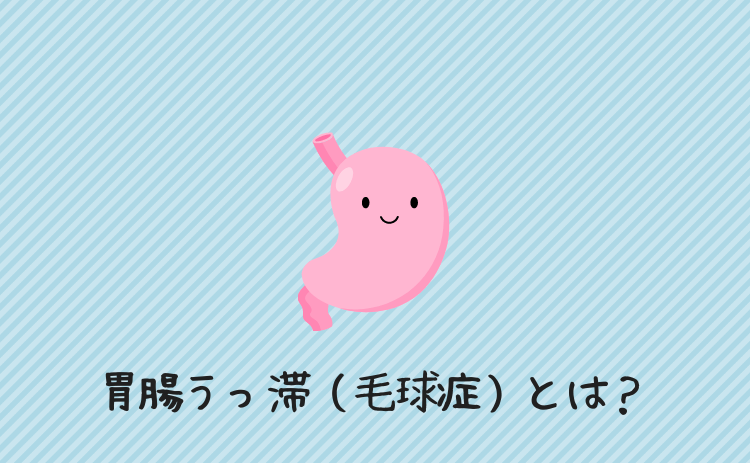
まずは、「胃腸うっ滞(毛球症)」とはなんなのか? から見ていきましょう。
草食動物であるうさぎさんの胃腸は、つねに動きつづけています。
しかしこれが、つぎのような原因によって(胃腸の働きが)停滞してしまうのが「胃腸うっ滞」です。
- 食べたものがあわず、おなかにガスがたまってしまった
- 季節の変わり目(換毛期)の温度変化で、胃腸炎などの体調不良を起こしてしまった
- 不正咬合などの歯の病気で、牧草をあまり食べなくなっていた(繊維質が不足していた)
- 短期間に(自然に排出できないほどの)大量の毛を飲み込んでしまった
- なんらかの痛み、ストレス、運動不足で胃腸の働きが低下していた
それで、この胃腸うっ滞になると、
- うんちが毛で数珠つなぎになっている
- レントゲン検査をしてみると胃の中に毛玉がある
などの症状がみられることから、もともとは「飲み込んだ毛が固まって胃腸うっ滞をおこしている」と考えられていました。



だから、うっ滞は「毛球症」とよばれていたと
けれども、正常な状態でも、うさぎさんの胃には(毛づくろいなどで飲み込んだ)毛はある程度たまっています。
加えて、うさぎさんの胃液は強力な酸性(多少の毛では詰まらない)です。
そこで、そういった理由もあって近年では、
- 飲み込んだ毛が固まって胃腸うっ滞が引き起こされる、ではなく
- 胃腸うっ滞が引き起こされるからこそ、飲み込んだ毛が胃で固まってしまう
と、認識があらためられるようになったわけです。
(※順序がちがう=毛球症というか胃腸うっ滞、というとわかりやすいかもしれません)



なので、毛球症という名称は使われず、
- 胃腸うっ滞
- 消化管うっ滞
- ウサギ消化器症候群/RGIS(うっ滞にかかわる症状の総称)
といった名称が、(うさぎの)おなかでモノが詰まる病気には使われるようになっています。
うさぎさんの「胃腸の働きが低下する順序と、それを引き起こす原因」が見なおされた、ということですね。
胃腸うっ滞の症状


では、うさぎさんがこの「胃腸うっ滞」になると、どのような症状がでるのか?
これはつぎのようなものがあげられます。
- 食欲不振になる(ご飯を食べなくなる)
- うんちが減る、でない、毛でつながったものがでる
- おなかをさわられるのを嫌がる、おなかが(ガスがたまって)張る
- うずくまって動かなくなる、ときどき体を動かすも落ち着かない、歯ぎしりをする
食欲が低下し、元気がなくなり、うんちをしなくなって、あまり動かなくなる……。
このような症状がみられたときは、胃腸うっ滞が起きている可能性は高いといえそうです。



換毛期とか、季節の変わり目とか、
このようなタイミングはとくに、胃腸のうっ滞は起こりやすいと感じます。
まったくご飯を食べてくれなくなるなど、見ればすぐにわかるレベルなので、これには注意しましょう。
新版 よくわかるウサギの健康と病気(誠文堂新光社)/ウサギの消化管うっ滞(毛球症)/うさぎの消化管うっ滞(毛球症)【獣医師監修】/うさぎの食滞(過去にいう“毛球症”)
うさぎが胃腸うっ滞になったらどうする?


(胃腸うっ滞らしき症状が確認されたイブスター店長)
ここまでの話で、胃腸うっ滞についての理解が深まりました。
それでは、うさぎさんがこのうっ滞になってしまったときは、どうすればいいのか?



つづいて、これを見ていきましょう
うさぎさんが胃腸うっ滞になってしまったときの対策方法は、つぎの2つです。
- 自然に治るのを待つ
- 動物病院に行く(おすすめ)
おすすめは動物病院へGOです。
が、自力で回復してくれることもあるので、具体的な対策とあわせて、それぞれくわしくお話しします。
1. 自然に治るのを待つ
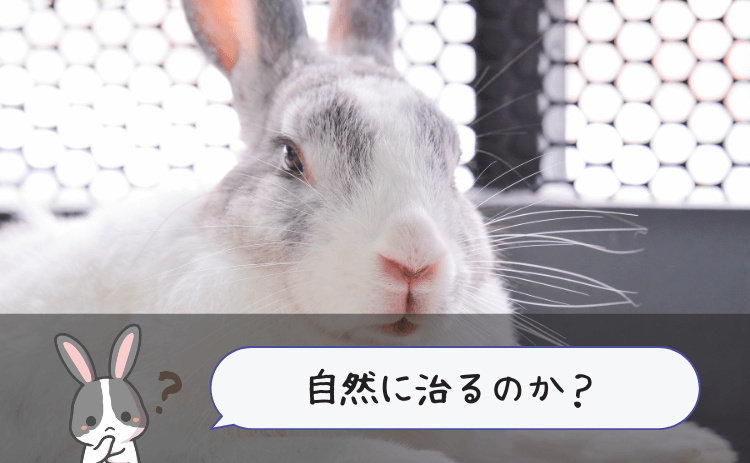
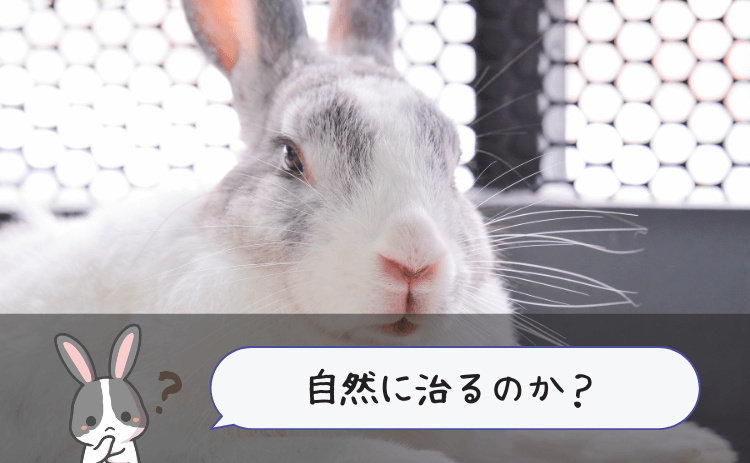
うさぎさんの胃腸うっ滞は、1~3日ほどで、自然に治ることはたしかにあります。
ですから、その回復を待つというのも選択肢のひとつです。
うっ滞になると、うさぎさんはほぼ餌を食べなくなってしまうでしょう。
でも、好物なら少量は食べてくれたりもするので、つぎのようにして食事・水分をとらせてあげ、
- おやつなどを食べさせて胃腸を動かす
- 野菜・果物を食べさせて水分補給をさせる
胃腸の働きと体調の回復を待つと。
(※おやつを手にのせて食べさせたり、新鮮な野菜・果物を食べやすいところにセットしておきます)
自然に回復する場合は、1~2日くらいで「食欲、うんち・おしっこの量」がもとにもどります。



事実、ミニレッキスのイブスター店長は、何度かこれで復活してきたので、
うっ滞からケロッと回復することは、じっさいにもあるわけです。
ただ、問題は、最悪の場合はうさぎさんが死亡する可能性もあるということ。
軽い胃腸うっ滞かと思っていたらそうではなく、もっと重い症状で、
様子見をしていたら手遅れになってしまった
なんていう危険性も、この自力での回復を待つ方法にはあるのです。
ウサギは24時間以上ご飯を食べないと、かなり危険な状態になるといわれているので、タイムリミット的な危険もあります。
ですから、胃腸うっ滞がうたがわれたら、
「動物病院に直行する」
これが、いちばんまちがいはありません。
以下の関連記事では、うっ滞が自然に治ったときの記録ものこしてあります。
けれども、さきのとおりで、この対処法にはリスクもあります。
チェックされるさいは「あくまで参考程度」ということで、ごらんになってみてください。



自然に治ることもあるが、「毎回うまくいくとはかぎらない」ということだな
胃腸うっ滞から回復したときの記録
2. 動物病院に行く


うさぎさんが胃腸うっ滞から回復するのを待つ方法は、万が一ということもあります。
ですから、最初から動物病院に行っておいたほうがまちがいはないでしょう。
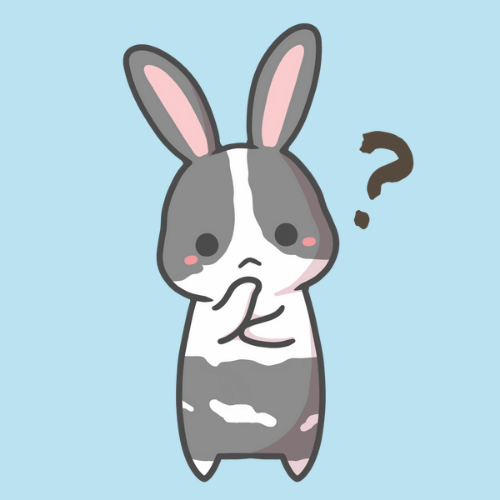
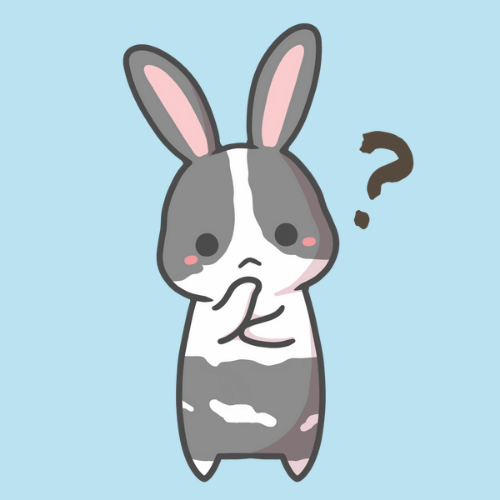
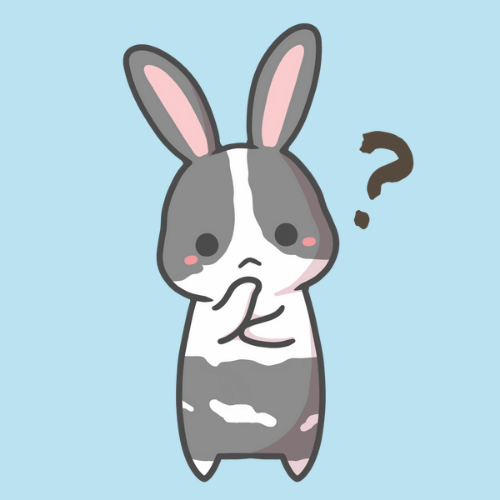
で、病院に行くとなにをしてもらえるんだ?
これは、つぎのような治療が受けられます。
- 点滴を打つ(水分補給や循環の改善)
- 整腸剤(胃腸運動の促進)や食欲刺激剤の投与
- 痛みを取り除く処置
- 強制給餌(強制的に餌を食べさせる)
- 外科手術(※ただし手術となる場合はすくない)
ちなみに胃腸うっ滞に関係するものに「胃拡張」という病気があります。
ガスがたまっておなかがパンパンに張れてしまう
というものですが、この場合は、強制給餌やマッサージは危険(逆効果)ともいわれています。
そのため、うっ滞のくわしい症状を確認するためにも、レントゲン検査がおこなわれる場合もありますよ。
気になる治療費は……やはり病院によっても異なります。
薬の処方だけなら数千円ですんだりもしますが、検査がある場合は数万円ほどになることも。



というわけで、病院に行くさいは、
ある程度の治療費は覚悟して(用意して)おいたほうがいいでしょう。
ペット保険があれば負担を減らせます
うさぎの胃腸うっ滞を予防する方法
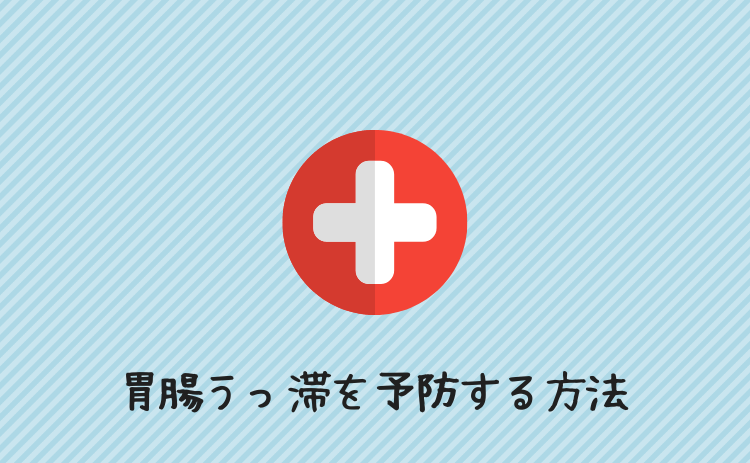
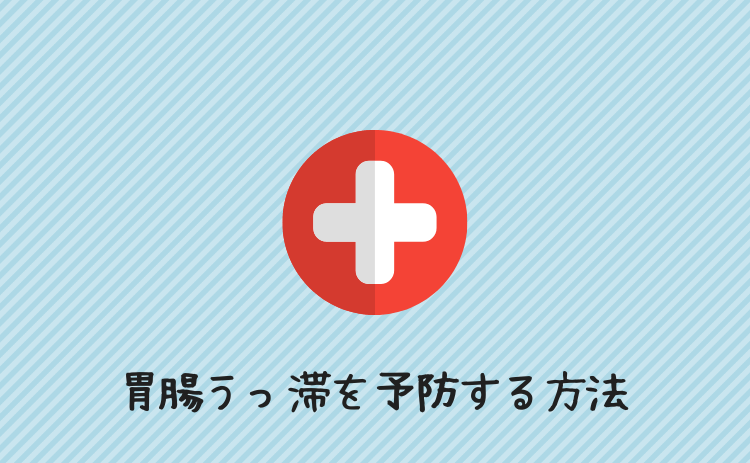
うさぎの胃腸うっ滞は命にかかわることもある病気で、病院に行くと安くはないお金がかかります。
ですから、この胃腸うっ滞は、ふだんから予防してあげるのがかなり重要になってきます。



そこで、これの予防策を最後にチェックしておきます
これは以下の方法が予防策として有効です。
- 牧草をたくさん食べさせる
- おやつは消化にいいものを選ぶ
- グルーミング(ブラッシング)をする
- 気温の急激な変化に注意する
- 散歩をさせて胃腸を活性化&ストレス解消
こちらも、それぞれくわしく見ていきましょう!
1. 牧草を食べさせる


胃腸うっ滞の最大の予防策は、大量に牧草を食べさせてあげることです。
うさぎさんの主食である牧草は、繊維質が豊富で、じつはつぎのような効果があるんですね。
- 不正咬合(歯が伸びすぎる)をふせぐ
- 腸内環境をととのえる(ガスの発生をおさえる)
- 胃腸の動きをよくする(毛などの排出を促進する)
不正咬合の予防は「牧草を食べない」の予防に。
腸内環境と胃腸の動きをよくするのは、うっ滞のダイレクトな予防になります。



ようするに、です
牧草をたくさん食べていれば、基本的にはうっ滞とはオサラバな生活を手に入れられる、ということです。
そんなわけですから、ふだんから牧草をモリモリ食べさせてあげてください。
うさぎさんによって好みの牧草は変わるので、牧草の選び方は、以下の関連記事も参考にしてみてくださいね。
ベストな牧草をチョイス!
2. おやつは消化にいいものを選ぶ


うさぎさんにあたえるおやつは、消化にいいものを選んであげましょう。
たとえば、つぎのようなものは、胃腸うっ滞の原因となることがあります。
- クッキーやビスケットなどの固形おやつ(小麦粉)
- 大麦・えん麦などのグラノーラ系おやつ(穀物・穀類)
固形おやつのつなぎとして使われる小麦粉は、消化にわるく、これがおなかのなかで固まってしまうことも。
また穀物・穀類は、食べすぎると異常発酵してガスがおなかでたまるなど、これもやはり胃腸うっ滞の原因に。



そういったこともあるので、
うさぎさんにあたえるおやつは、野菜・果物・無添加のものなど、安心安全なものにしたほうがいいです。
こちらも以下の関連記事でまとめてあるので、あわせてどうぞ!
(※ちなみに、パパイヤ酵素やパイナップル酵素が毛玉にいい、という話があるのですが、これの真偽はさだかではないそうです)
うさぎのおやつの選び方
3. グルーミング・ブラッシングをする


うさぎさんが大量の毛を飲み込んでしまわないように、とくに換毛期などは、せっせとブラッシングをしてあげましょう。
毛球症うんぬんでも見てきたように、多少の毛なら、うさぎさんは飲み込んでも問題はないようです。
ただ、それがあまりにも多いと、やはりこれも胃腸うっ滞の原因となってしまうこともあるといいます。



だから、ブラッシングで抜け毛をとってあげるわけだな
うさぎさんのブラッシングは、ブラシが1本あればすぐにでもできます。
こちらも方法はまとめてあるので、やり方がわからないときは、ブラッシング・グルーミングの方法をチェックしておいてください。
4. 気温の変化に注意する
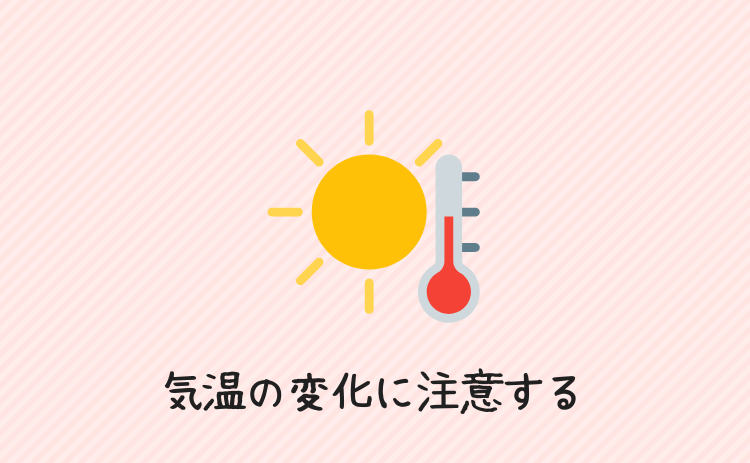
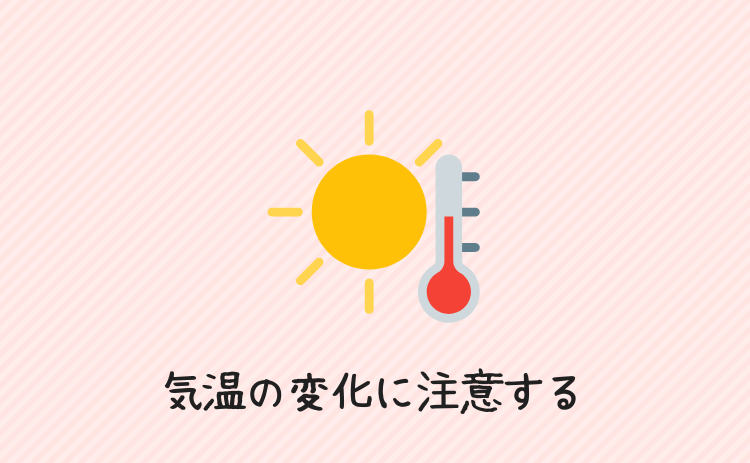
うさぎさんが胃腸うっ滞になるのは、気温が急激に変化したときが多いと感じます。
そのため、季節の変わり目などは、温度変化には気をくばってあげるようにしましょう。
具体策としては、暑くなってきたり、寒くなってきたりしたら、すぐにエアコンで温度調節してあげることです。



うさぎさんにとっての適温は15~25℃くらいともいわれるので、
それくらいになるように、温度管理をしてあげましょう。
電気代をケチっていると、そんなものの比ではない治療費が必要になることもあります。
これらも参考に、一年をとおして、うさぎさんが快適に過ごせる環境をつくってあげてくださいね。
5. 散歩をさせる


そして最後に、うさぎさんを毎日散歩させてあげましょう。
胃腸の動きもよくなり、ストレス解消にもなるなど、適度な運動は胃腸うっ滞の予防になるからです。



どれくらい散歩させてあげればいいかというと、
最低でも1日に1時間くらいはさせてあげたいところです。
時間がないときは30分×2セットとか、とにかくケージから出してあげる時間をつくってあげてください。
運動すればおなかも空きますし、こうすることでも、牧草を食べる量を増やしてあげられます。
変なものを食べてしまわないように気をつけながら、お部屋のなかを歩きまわらせてあげるといいですよ。



運動したあとのメシはウマい!!
うさぎの散歩のさせ方
今回のまとめ
- うさぎは胃腸うっ滞になるからおなかで毛玉ができる
- うっ滞は自然に治ることもあるが、病院に行ったほうが安心
- ふだんから予防することでうっ滞とはオサラバな生活に!
個人的に、うさぎさんがなりやすい病気のNo.1は、この「胃腸うっ滞」です。
動物病院によっては、毎日のように、うっ滞のうさぎさんが運ばれてくるのだとか。
それだけ、このうっ滞は、日常的に起こりやすい病気だといえるのではないかと思います。
ふだんから予防してあげていれば、うっ滞にならない生活も送れるようになるはずです。
ぜひ、うさぎさんの健康に気をくばってあげ、元気ハツラツな胃腸生活をゲットさせてあげてください。



ただ、いくら予防していても、なるときはなります
そんなときは、たしかに自然に治ることもありますが、病院に連れていってあげたほうがまちがいはありません。
不安なときは、病院に行くだけも安心できます。
自力での回復にこだわる必要もないので、より安全な対策をとってあげるのがおすすめですよ。
ベストな牧草の選び方
不正咬合にも注意!
ペット保険に入れば安心!

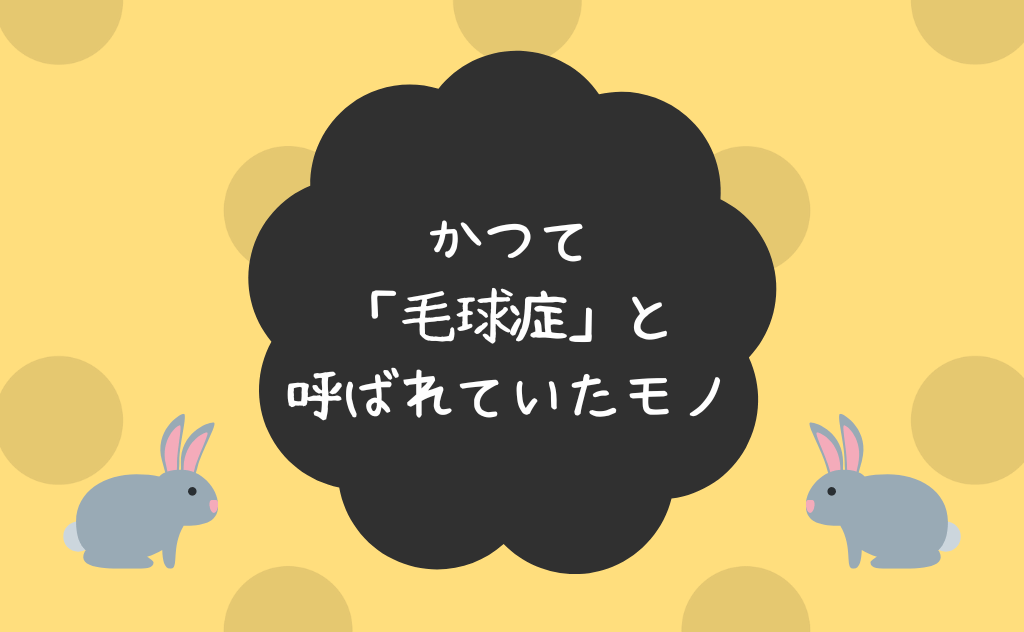
コメント(確認後に反映/少々お時間をいただきます)